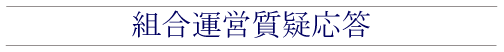加入金の性格について
質問事項
事業協同組合模範定款例によると、脱退者の持分の払い戻しについて各組合員の出資額を限度とする組合は、加入金についての項目を削除することとされている。このことにより加入金は徴収できないと考えられるが、どうしてなのか。
回答内容
事業協同組合の組合員は、定款で定められた出資1口金額について、必ず1口以上出資しなければならないことになっている。
組合は、それら組合員の出資により、事業を行うための施設等を保有する一方、剰余を内部に留保したりして、組合財産を形成していくことになる。
したがって、組合の財産は組合員全員の共有のものであるので、組合の正味財産(必ず時価によって算定しなければならない。)を組合保有の全出資口数で除した金額か出資1口に対する持分額となる。
このようにして計算された持分額が定款で規定されている出資1口金額より多い場合は、加入を希望する者から持分調整金として加入金(その差額)を負担させないと組合員間に不利益を生ずることになるので、このような場合には加入金を徴収することができるとされている。
しかしながら、持分額が出資1口金額より多い場合であっても脱退者に対する持分払い戻しが「各組合員の出資額を限度とする」組合にあっては、組合員間に不利益は生じないため、加入金を徴収する必要はないので削除することとしているのである。
なお、この考えは出資を伴う他の組合、連合会にも適用できるとされている。 また、加入に当たって徴する諸雑費等の事務手数料は「加入金(資本勘定)」ではなく、「加入手数料(事業外収益勘定)」として取扱われることを付記しておく。